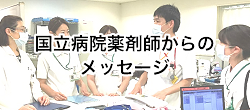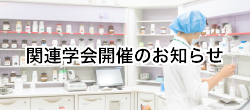関信地区国立病院薬剤師会 各施設の詳細は、こちらのページからご覧下さい。
| 感染制御認定薬剤師 |
| 東京理科大学 2016年卒業 |
|
| A . S |
| 東京医療センター |
|
1) 普段はどんな仕事をしていますか?
薬剤部の業務に加えて、感染制御専門薬剤師として感染対策チーム(ICT)と抗菌薬適正使用支援チーム(AST)の一員として活動しています。ICTでは院内感染を防止するため、定期的な院内ラウンドを行い、院内の環境整備や標準予防策・手指衛生の指導などを行っています。ASTでは週3回のカンファレンスを行い、抗菌薬の適正使用を通して薬剤耐性菌を作らないための診療支援を行っています。薬剤部内では、病棟薬剤師と連携して抗微生物薬のTDMを行ったり、調剤や病棟における感染症関連の相談にのったりしています。
2) 職場の雰囲気は?
ICT/ASTの実働部隊は医師、看護師、薬剤師、微生物検査技師などの多職種で構成されており、気軽に相談できる関係性が築けています。カンファレンスで検討した症例について、各自が調べたガイドラインや論文を共有し、知識のアップデートも行っています。それぞれの専門性を活かして高め合えるチームです。
3) 仕事のやりがいは?
感染症は誰にでも起こり得るため、日常で感染症関連の知識が活かされる場面が多くあります。近年ではCOVID-19対応や、能登半島地震における避難所の感染対策業務にも携わりました。活動の幅が広いのもやりがいの一つであると感じています。
4) 今後の目標や夢は?
日々のICT/AST業務を通じて、予防・治療の両面で感染症診療の一助となれるよう尽力するとともに、後輩薬剤師の育成にも努めていきたいと考えています。
5) 薬剤師を目指す学生へのメッセージ
私は国立国際医療研究センター病院で薬剤師レジデントを修了し、感染制御認定・専門薬剤師の資格を取得後、現在の東京医療センターに赴任しました。施設によって感染対策も様々であり、前職での経験を活かして業務に取り組んでいます。国立病院機構は様々な特色をもった施設があるので、自分の興味のある分野を見つけ、薬剤師としての専門性を磨いてみませんか?ぜひ一緒に頑張りましょう!
|
ページトップへ戻る
| 精神科薬物療法認定薬剤師 |
| 東北薬科大学 2001年卒業 |
|
| H . S |
| 東京医療センター |
|
東京医療センターは、640床を有する総合病院であり、地域がん診療拠点病院、東京都災害拠点病院の機能を有するとともに、救命救急センターでは3次救急の受け入れを行う地域の中核病院になります。その中で、精神科薬物療法認定薬剤師として、メンタルケア科を主体としたリエゾンチーム、認知症ケアチーム、せん妄対策チーム、身体抑制最小化チームへ参画をしています。リエゾンチームでは、手術目的で入院された患者がせん妄を発症した際に、処方提案や環境調整等を提案しています。そのほか、過量服薬(オーバードーズ)患者に対して、薬学的観点から今後起こりうる副作用を推論し、病棟薬剤師に血中濃度測定が必要な薬剤の採血依頼や、身体症状が安定した際には常用薬を再開するタイミング等を提案しています。また、精神疾患を抱えながら、手術や抗がん薬の治療を目的に入院を必要とする患者への心理的サポートや薬物療法支援等も行います。身体診療科には、抗精神病薬や向精神薬の取り扱いは難しく、リエゾンへの介入依頼は多くあります。特に、ベンゾジアゼピン系薬剤の多剤併用事例では、安全に減量・中止もしくはスイッチングを行えるよう医師と十分な協議を行うと共に、減量中には患者がベンゾジアゼピンによる離脱症状を起こさないよう定期的な薬物モニタリングも実施しています。私は、さいがた医療センターで精神科薬物療法認定薬剤師を取得後、現在の東京医療センターに赴任することとなりました。精神科専門の施設から総合病院への転勤には不安もありましたが、患者の悩みに共感し支援することは精神科のみならずどの診療科にも言えることかと思います。周術期医療、がん薬物療法のほか救命救急医療を基盤とし、精神科医療にも携わることができる総合病院を当院では実践しています。
|
ページトップへ戻る
| 妊婦・授乳婦認定薬剤師 |
| 東北薬科大学 2007年卒業 |
|
| N . S |
| 国立成育医療研究センター |
|
1)普段はどのような仕事をしていますか?
調剤業務と薬剤管理指導業務、また周産期病棟の常駐薬剤師として業務しています。
患者さんのなかには妊娠・授乳期の薬剤使用に対する不安から服薬を我慢したり、自己判断で服薬を中止して基礎疾患を悪化させたりしてしまう方がいます。添付文書等の妊婦・授乳婦の項だけでは患者さんを納得させる説明が難しいため、現状に即した情報収集を行い医師と協議して説明することがあります。
2)職場の雰囲気は?
当院は小児と周産期の専門病院のため、複雑な散剤調剤や混注業務が多くあり、日々緊張感をもって調剤しています。薬剤部内では積極的に研究や学会発表に取り組んで切磋琢磨しています。病棟では常駐を始めてからより一層、医師や看護師から薬剤の相談を受ける機会が多くなりました。またカンファレンスでは多職種間で情報交換を行い、患者のより良い治療のために連携しています。
3)仕事のやりがいは?
薬物治療が必要な妊婦・授乳婦さんに適切な情報提供を行い患者さんに正しく理解してもらえた時にとてもやりがいを感じます。また、無事に赤ちゃんを出産された様子を見られた時には安堵と喜びがあります。
4)今後の目標や夢は?
妊娠期の薬剤使用の情報提供は難しいリスクコミュニケーションが求められるため、さらに技術を磨いていきたいと思います。また、妊婦・授乳婦薬物療法専門薬剤師を目指して未来の妊婦・授乳婦さんの役に立つ研究を考えたいです。
5)薬剤師を目指す学生へのメッセージ
国立病院機構には幅広い分野を学べる総合病院から専門性の高い病院まで様々な施設があります。薬剤師としては一つ一つが貴重な経験になるのでそこから多くのことを学び、患者さんの治療に貢献できるスキルを身に付けていってください。
|
ページトップへ戻る
| HIV感染症薬物療法認定薬剤師 |
| 千葉大学 2016年卒業 |
|
| M . K |
| 国立国際医療研究センター病院 |
|
1)普段はどのような仕事をしていますか?
当院には、薬害エイズ訴訟の和解を踏まえ、被害者救済の一環としてエイズ治療・研究開発センター(AIDS Clinical Center, ACC)が設置されています。最先端の医療を提供するだけでなく、新たな診断や治療の開発のための臨床研究、基礎研究を行っています。
現在HIV感染症は、治療継続によりコントロールが可能な慢性疾患と言われています。患者さんが安心して薬物治療を継続できるよう、直接の服薬指導だけでなく、薬物間相互作用の確認、新薬を含む薬剤情報の提供、処方提案、薬物血中濃度の測定など幅広い薬学的介入を行っています。
ACCは全国の医療従事者に対する研修会を実施しており、薬剤師も講師として参加しています。薬剤部としても全国の拠点病院や近隣の保険薬局と連携し、情報発信を積極的に行っています。
2)職場の雰囲気は?
ACCでは医師、看護師、薬剤師だけでなく、臨床心理士、社会福祉士、歯科衛生士など多職種で患者さんをサポートしています。顔の見える関係性で、お互いに気になったことを気軽に質問できる雰囲気です。
3)仕事のやりがいは?
薬剤師としての情報提供や処方提案が治療方針に活かされたり、患者さんとお話することで安心して治療を受けてもらえたりすることです。
4)今後の目標や夢は?
HIV感染症や日和見疾患だけでなく、幅広い薬学的な知識・技能を身に着け、より良い薬物治療を患者さんに提供できるようになること、また研究も継続的に実施していくことが目標です。
5)薬剤師を目指す学生へのメッセージ
病院薬剤師は、様々な医療従事者と関わることができ、多方面から患者さんをサポートすることの意義を実感することができます。また日常診療に加え、興味のある分野のスペシャリストを目指し新しいことに挑戦する多くの機会に恵まれています。ぜひ病院薬剤師に興味を持っていただき、視野の広い医療従事者になるために一緒に頑張りましょう。
|
ページトップへ戻る
| がん薬物療法認定薬剤師 |
| 明治薬科大学 2013年卒業 |
|
| D . I |
| 相模原病院 |
|
1) 普段はどのような仕事をしていますか?
私は普段、外来治療センター・病棟等でがん治療に関わる業務を行っています。具体的には、外来治療センターでの診察前面談、病棟での服薬指導、レジメンチェック、抗がん薬調製などです。特に当院では診察前面談に力を入れており、医師の診察前に看護師同席で副作用評価等を行い、処方提案や処方支援を積極的に行っています。また、レジメン管理や院外薬局との連携を通して、安全・安心ながん薬物療法提供体制の構築に努めています。
2) 職場の雰囲気は?
薬剤部内は幅広い年齢の職員が在籍しており、困った時は皆で助け合いながら業務を行っています。また、認定・専門資格を有する薬剤師が複数在籍しており、専門性を活かした業務を積極的に展開しています。
3) 仕事のやりがいは?
がん薬物療法では、患者さんに様々な副作用が出現する可能性があります。そのため、薬剤師として患者さんの訴えや状態から問題点を把握し、処方提案や処方支援を通して患者さんの症状改善や治療継続に貢献できた時にやりがいを感じます。
4) 今後の目標や夢は?
がん薬物療法は日進月歩しているため、常に知識をブラッシュアップすることで患者さんに最善のがん薬物療法を提供できるように引き続き精進していきたいと考えています。また、後進の育成や研究を行うことで、より安全・安心ながん薬物療法を提供できるよう、尽力したいと思っています。
5) 薬剤師を目指す学生へのメッセージ
国立病院機構には多様な施設があることから、がん薬物療法認定薬剤師だけではなく、様々な認定取得のチャンスがあります。一方で、認定取得に当たっては年単位での計画が必要となるため、興味がある分野があればチャンスを逃さず、積極的に挑戦してみて下さい。そんな皆さんを後押しする環境が国立病院機構にはあります。皆さんと一緒に働ける日を楽しみにしています。
|
ページトップへ戻る
| 緩和薬物療法認定薬剤師 |
| 帝京平成大学 2017年卒業 |
|
| M . H |
| 千葉医療センター |
|
千葉医療センターは病床数410床(緩和ケア病棟20床含む)、診療科数25科の地域医療支援病院で、地域がん診療連携拠点病院、地域災害拠点病院、エイズ治療拠点病院等に指定されている病院です。薬剤師は24名(産前産後休業者・育児休業者含む)在籍しています。多種多様な資格を取得している薬剤師が多く在籍しており、互いに相談し、協力し合いながら業務を行っています。日常業務の相談だけでなく、臨床研究・学会発表や資格取得の相談もできる環境です。
私は現在、救急病棟の専任薬剤師として病棟薬剤業務・薬剤管理指導業務を主に行っており、その傍らで調剤業務、外来業務も行っています。また、チーム医療では緩和ケアチーム及びHIV診療チームを担当しており、業務内容は多岐にわたります。
当院の緩和ケアチームでは毎週2回、緩和ケア科医師、精神科医師、緩和ケア認定看護師、管理栄養士、理学療法士、薬剤師の多職種でカンファレンス及び回診を行っていますが、緩和薬物療法認定薬剤師の活躍の場は緩和ケアチームだけではありません。薬剤部内では、後輩からだけでなく先輩からも相談を受けることがしばしばあります。病棟では緩和ケアチームのメンバーではない看護師、親しい医師からも相談されることがあり、いつの間にか「緩和のことといえばM・Hさん」という風潮になっていることにやりがいを感じ、誇りに思っています。
今後は緩和医療専門薬剤師の資格を取得し、緩和医療領域のスペシャリストになることを目標としており、後進の育成にも取り組んで参ります。
国立病院機構には規模や特色の異なる病院が全国にあり、幅広い分野の知識を習得できる機会、人脈を広げることのできる機会があります。就職先の選択肢の一つとして、ぜひ国立病院機構をご検討いただけますと幸いです。
|
ページトップへ戻る
| 小児薬物療法認定薬剤師 |
| 大阪薬科大学 2017年卒業 |
|
| H . N |
| 埼玉病院 |
|
1)普段はどのような仕事をしていますか?
昨年度まで育児休暇を取得しており、今年度から育児時間制度を使用して勤務しているため、現在は調剤業務や病棟薬剤業務をメインに働いています。病棟薬剤業務では小児科を中心として、NICU・GCU・産婦人科なども担当しています。
2)職場の雰囲気は?
当院の薬剤部には様々な認定・専門薬剤師の資格を取得している方が多いため、自分の薬識が足りず困った場合でも気軽に相談できて心強いです。また、資格取得の後押しもしてもらえる環境だと感じます。私は小児薬物療法認定薬剤師の資格を取得しましたが、既に同資格を取得している先輩に試験勉強の方法や資格取得後の症例報告の記載方法などご教示いただき、手厚くサポートしてもらえて有難かったです。
病床数が550床と大規模病院ですが、多職種間でもコミュニケーションが取りやすいアットホームな雰囲気だなと感じます。病棟でも医師に処方や投薬方法の提案などを行ったり、小さなことでも医師や看護師と報告や相談をし合ったりと、皆で協力しながら治療を進めていくことが多いです。
3)仕事のやりがいは?
小児科での病棟業務で拒薬のひどい患児を担当することが多く、本人も保護者の方も疲弊しておられる場面に度々直面します。何が原因で拒薬となっているのか?投薬方法は服薬補助食品を使用するのか、もしくはご褒美制度(内服できたらシールを与えるなど)を使うのか?退院後のアドヒアランスを継続するにはどうすればよいか?など考え、投薬方法を提案し、入院中に拒薬が解消されると自分事のように嬉しいです。患児にとって薬が“嫌いなもの”から“味方”へと、意識が少しでも変わってくれるといいなと思いながら仕事をしています。
4)今後の目標や夢は?
小児科領域について更に専門性を高めてスキルアップしていきたいです。
5)薬剤師を目指す学生へのメッセージ 私は結婚を機に住居が関西圏から関東圏に変わったのですが、国立病院機構内でブロック異動をさせてもらい、キャリアを継続することができています。また、産前産後休業や育児休業(最近は男性も取得されている方が多い印象です)や育児時間制度など、福利厚生もしっかりしているのでライフステージが変わっても働きやすいです。是非就職先の候補の一つにしていただければと思います。
私が緩和ケアに携わる中でやりがいを感じるのは、患者さんの苦痛が緩和されて笑顔が見られたときや、病を患いながらも一日一日を大切に過ごしている患者さんの人生に深く関わることができたときなどです。そういった気持ちを、一緒に悩みながら活動するチームメンバーと共有できるのも緩和ケアの魅力です。★国立病院機構には専門性の高い施設が沢山ありますが、様々な分野のジェネラルな知識の上にこそ専門性が成り立ちますので、これから薬剤師を目指す方には、幅広い視点を持って学んで頂けたらと思います。そして、がん診療に携わるすべての方が緩和ケアに関心を持ち、その中から志ある方が緩和ケアの普及や発展を目指して、一緒に活躍してくれることを願っています。
|
ページトップへ戻る
| NST専門療法士 |
| 昭和大学 2017年卒業 |
|
| M . Y |
| 久里浜医療センター |
|
1) 普段はどのような仕事をしていますか?
当院は精神科疾患の治療を提供におり、統合失調症やうつ病に加え依存症(アルコール、ギャンブル、ネット等)、認知症を対象とした設備があります。
特にアルコール依存症患者は入院初期に低栄養、電解質異常が顕著に現れるため、点滴での補正が必須となります。
私が担当している病棟には高齢者が多いため、認知機能や嚥下機能の低下が見られる患者が多く末梢からの点滴が不可能など栄養管理する上で様々な困難が発生します。
CVポートの挿入や胃瘻造設を自施設で行えず、選択肢の少ない中で普段から患者にとって最適な栄養療法を検討し医師や看護師などの多職種と連携しています。
2) 職場の雰囲気は?
中規模病院で多職種と連携がとれており、強い関係性を構築できることが魅力的です。
カンファレンス以外にも気軽に相談し、情報共有がスムーズに行われ、互いの専門性を活かした診療がわれています。
3) 仕事のやりがいは?
低栄養状態の患者が栄養状態改善していく姿をみると嬉しく思います。
また、チーム医療の一員として携われることにやりがいを感じています。
4) 今後の目標は?
次年度から病院としてNST構想があり現在は準備をしています。
今後はNSTの一員として、今まで介入できなかった症例にも介入することや後進の指導・育成に注力していきたいです。
5) 薬剤師を目指す学生へのメッセージ
国立病院機構は幅広い分野を学べる総合病院と専門性が高い病院など様々な施設があります。私自身も前職場では急性期医療を、現在は統合失調症や依存症などの精神疾患の治療に貢献しています。異動により様々な分野に触れることができるのも国立病院機構の強みです。意欲溢れる皆さんと一緒に働ける日を楽しみにしています。
|
ページトップへ戻る
| 救急認定薬剤師 |
| 明治薬科大学 2014年卒業 |
|
| M . S |
| 宇都宮病院 |
|
1) 普段はどのような仕事をしていますか?
私は主に、調剤業務、製剤業務、医薬品の適正使用や採用などに関する医薬品情報管理業務を行っています。また、入院患者さんに対しては、個人に合わせた投与量の提案や、注射薬の配合変化やルート管理など、他職種と協力して治療に介入しています。
2) 職場の雰囲気は?
当院は結核、重症心身障害児、神経難病の病床を有する二次救急医療機関で、10名の薬剤師が在籍しています。さまざまな認定や資格を有する薬剤師が在籍しており、それぞれの得意分野を活かしながら、またお互いに相談しながら患者さんの治療に携わっています。
3) 仕事のやりがいは?
緊急性や重症度の高い患者さんの治療に関わることが多く、責任感を強く感じることも多々あります。他職種と密に連携をとり、薬剤師としての職能を発揮し、患者さんの治療が上手く進んだ際には達成感を感じます。さらに、救急・集中治療領域では全身管理を行うために幅広い薬剤の知識が必要ですが、その知識や経験を医薬品情報管理業務などにも活かせていることもやりがいの一つになっています。
4) 今後の目標や夢は?
今後は自身のスキルアップとともに後進の育成に尽力し、救急専門薬剤師の資格取得を目指しています。さらに、栄養や感染に関する認定も取得を考えています。
5) 薬剤師を目指す学生へのメッセージ
専門分野は多数ありますが、救急・集中治療領域でも薬剤師の必要性が認識され、救急認定・専門薬剤師制度が10年ほど前から実施されています。病棟だけでなく救急外来や手術室など、薬剤師が必要とされる部門も増え、チーム医療の中での活躍が期待されています。救急・集中治療領域に関心のある方、ぜひ一緒にスキルアップしていきましょう。
|
ページトップへ戻る
| 褥瘡認定薬剤師 |
|
城西大学 2009年卒業
城西大学大学院 2011年卒業
|
|
| M . A |
| 西新潟中央病院 |
|
褥瘡は骨突出部に持続的な圧迫が加わることでできる潰瘍であり、痛みを伴うことも多く患者のQOL低下の原因となることもあります。そのため、適切な治療を行い早期に治癒することが望まれます。褥瘡は個々の患者で発生要因や体格、環境などが異なるため多職種で協力して多角的に予防・治療にあたっています。
実際に業務で褥瘡治療に関わっているのは、月1回の褥瘡対策チーム会と病棟からの褥瘡治療薬の相談がメインとなります。褥瘡対策チーム会の症例検討会ではチームメンバーと創部写真を観察し、病棟の褥瘡患者では直接創部の確認を行い、薬剤提案や処置方法について医師や看護師とディスカッションをしています。
褥瘡治療薬は主薬の効果と軟膏基剤の特性の組み合わせで治療効果を示します。薬剤師として、褥瘡の早期治癒のため個々の患者の褥瘡に合わせた薬剤を処方提案できるように知識の取得と更新が必要となります。そのためには学会や研修会などに参加することが効果的です。多職種が集まるチーム医療で薬剤師の処方提案が受け入れられ、褥瘡が治癒に向かうことにやりがいを感じます。
現在は創面の状態に合わせた単剤を処方提案していますが、創面の水分量に合わせてより細かい調節ができるブレンド軟膏を使用した治療方法も報告されているため、今後はそのようなブレンド軟膏についても処方提案できるようになりたいと考えています。
大学ではあまり教わらない分野だと思いますが、褥瘡の分野でも薬剤師が活躍できるチャンスがありますので、興味を持って勉強してもらえたら嬉しいです。
|
ページトップへ戻る
関信地区国立病院薬剤師会 各施設の詳細は、こちらのページからご覧下さい。